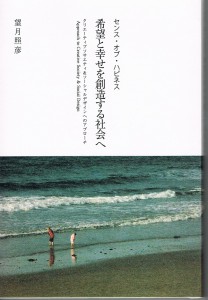- TOP
- 生活文化創造都市推進事業
- 生活文化創造都市ジャーナル
- 生活文化創造都市ジャーナル_vol.14 「ゆっくり小さく、美しく」 ―幸せな地域社会(コミュニティ)を創る叡智をー
生活文化創造都市推進事業
生活文化創造都市ジャーナル_vol.14 「ゆっくり小さく、美しく」 ―幸せな地域社会(コミュニティ)を創る叡智をー
エッセイスト 望月照彦氏

第1章 地方都市がデザインする「低速度社会」の意味とインパクト
社会はいま、文明クライシスに直面していると思えてならない。高度な技術文明が頂点に達すると、シンギュラリティ(技術特異点)が超文明を生み出すと予測されているが、一方ではカタストロフ(破局)も誘発されて起こると考えられているのである。シンギュラリティについては、アメリカの未来学者レイ・カーツワイルが『ポスト・ヒューマン誕生(2007年)』という著作で、人類は2045年にはコンピューターの性能が幾何級数的に高まり、人間の能力を凌駕する、と唱え人間の脳の限界を超えた超脳世界を描いて、衝撃を与えた。人間はロボットに命を移し替えて生き残る、というシナリオは確かにショッキングであった。しかしこの考え方に対して言語学者のノーム・チョムスキーは「空想かファンタジーに過ぎない、信ずべき何の根拠もない」と一蹴している。計算機能を基盤とするコンピューターから生み出されるAIは、複雑な感情を持つ人間の頭脳には原理的に到達することはない、とするのだ。カーツワイルと逆の発想を持つフランスの思想家ポール・ヴィリリオは、通信技術(情報)の急速な発達による世界の電脳化は、予測不能な地球規模の崩壊をもたらす可能性を持つ、として著作『電脳世界(1998年)』で警鐘を鳴らしている。世界的な情報化による全壊的な偶発事故の可能性(金融経済破綻や原発事故、世界戦争の勃発など)は、この地球世界の進歩の弊害を推測させる究極の啓示だ、とするヴィリリオの言説にも衝撃を受ける。ヴィリリオは、そうならないための抵抗(レジスタンス)の必要を説いているが、私はそうならないための社会的な強靭性(レジリエンス)を持つ必要性を考えるのである。
ヴィリリオは、実にユニークな「ドロモロジー」という考え方を提出しているが、これは「速度によって国家も社会も組織も個人の生活も、背後から駆動され突き動かされている社会構造」を意味している。そこでは「速度」は資本化され、権力や富やビジネスと結びつき専制支配を増幅させる有力なツールとなるわけだ。すなわち端的にいえば「早い者勝ち社会」を生み出すということになる。
世界は、スピードという概念に席巻されている。何事につけ、スピード優位社会である。飛行機や自動車、鉄道のスピード競争に代表されるような「スピード社会」はどう決着されるべきか。私の考えを選択すれば<立ち止まる>、ということがその一つである。そしてベクトルを、逆に向けて反転することである。そう、スピードではなく、「スローモビリティ社会」を構想することである。既に、イタリアで起こった「スローフード」運動は通念化しているが、ヴィリリオの速度概念は、驚くべきことに「世界の老化(社会の萎縮、縮退)」を意味するから、時間をゆっくりさせることは、若返りの創造を実現することに繋がる、と考えてもよい。
その社会の<若返りの実験>に挑戦している日本の都市がある。それが、群馬県桐生市の中小企業群などコミュニティセクターのトライアルである。

これまでに、桐生市は『ファッションタウン構想』の運動を20年以上継続して大きな実績を上げているが、私はその運動の立ち上がりから委員会メンバーとして協力してきた。「ファッションタウン構想」とは、1990年代当時の通産省(現経産省)が繊維産業を基盤とする産地の再生・復活を目指して始めた政策で、繊維産業にとどまらない地域の多様な地場産業と市民の生活文化をリンクして次世代のまちづくりを目指したものであった。全国で20都市を超えて指定されたが、桐生市のこの活動はこれまでにずっと先行モデル的な役割を果たしてきた。2017年が構想開始から20周年であったが、本年度の21年目の記念講演を私は依頼され、初夏の季節に桐生の街を訪れた。
その折に桐生商工会議所の石原雄二専務理事にぜひ体験してもらいたいものがある、と言って乗せられたものがあった。「MAYU(まゆ)」という愛称のいかにもかわいらしい電気自動車である。5月の爽やかな風のように、ゆっくりとした速度で桐生の街と商業・産業集積、古民家と郊外の古刹を巡る小さな旅をした。10人乗りのボックス型電気自動車は速度が最高でも19kmしか出せない。ときどき道の傍に留まるのは、後ろから追いついてくる自動車や自転車に追い抜いてもらうためである。先を急がない哲学が、このスローモビリティを旨とする自動車の信条で、街の風景も歩いている人の様も、のこぎり屋根の織工場や自然の中に埋もれて建っている寺院も、これまでの観光シーンとは全く違って心の中に悠然としみ込んでくる。ああこれは、スローツーリズムという新しいカテゴリーの旅が存在するのだ、と私には思えたものだ。
繰り返し言えば、現代はスピード過剰の時代、あらゆるものが、早く早くである。飛行機や自動車のような乗り物だけでなく、企業、産業の商品開発もスピードが勝負。Eコマースも通販も、ネットで注文すればその日のうちに届くといった具合。問題なのは、スピードを旨とするシンギュラリティ時代のAI技術の幾何級数的な進展に多くの人々が追いついていけなくなる「テクノクライシス(技術破綻)」が起こるのではないか、ということだ。実際に、パソコンを操作できずスマホを持たない人々にとって、生きづらい社会が生み出されている(アナログライフを信条とする仙人的人間もいるのかも知れないが)。それを技術リテラシー格差として見放してよいのだろうか。
桐生のMAYUプロジェクトは、桐生市の地域の経済・産業、それに織(おり)の都市が培ってきた地域文化の再興を目指して、地元の中小企業や大学に市民、そして行政、商工会議所等コミュニティセクターが「知活(叡智の出し合い)連携」して挑戦してきた事業である。国の関連事業政策も、大いに役割を果たしてきたし、活用もしてきた。また桐生市の取り組みには、アナログ的な世界観も大切にする伝統的、地縁的ローテクノロジー(人間的技術)への親和性を感じることができる。無論、スピード社会の持つ意味性も十分に視野に入れながらの開発であることは、論を待たない。
事業の具体的な取り組みは、株式会社桐生再生(事業のマネジメント)、株式会社シンクトゥギャザー(MAYUバスを始めとした先端的電気自動車の開発製造)、群馬大学理工学府(織機の伝統技術を電気自動車などの多様なテクノロジーにトランスファーする開発研究)、桐生市(都市計画における重要な施策立案)、桐生商工会議所(地域中小企業のまとめ役とバックアップ)等のコラボレーションによって進められている。MAYUバスを運営している桐生再生社長の清水宏康氏にバスに同乗してもらい、ゆったり揺られながらMAYUバス開発秘話を聞いた。その骨子は「桐生市では産業技術が多数の地元中小企業に集積し、今回のプロジェクトの中心になったシンクトゥギャザーの宗村正弘社長の技術開発力を軸にしながらその技術文化環境に育ってきた若手市民ベンチャーの叡智も活かし、群大理工学府の協力も得て観光や地域福祉に役立つ市民事業としてスタートした。スロー社会の先取りは、実は新しい文明の中核技術や産業に大きな影響を与えるでしょう」。
MAYUバスは観光だけでなく、本領は高齢化したコミュニティの人々の生活基盤づくりにある。この地域は市の中心部の周域にいくつものコミュニティ(村落)が存在し、そこに暮らす高齢者・子供たちの日常生活の足としてMAYUバスが機能することを行政や商工会議所、関係者が意図し、地域持続と幸せな暮らしのインフラとして考えているのである。
海外からも、特にアジアの国々からこの思想に共鳴し、「地域共生バス」として活用を想定する注文があって、有力な輸出製品になっていくのではないかと私は予測する。桐生という地方都市から途轍もないファッションタウン構想を根っ子にした「未来社会構想」が生まれていることに強い感銘を受けたのであった。
桐生市には、知識人と呼ばれる方々のファンが多い。シャープな文明評論を展開した西洋史家の木村尚三郎先生や、博覧会プロデューサーの泉真也先生などである。木村尚三郎先生の著作に『ふりかえれば、未来』があるが、過去の地縁技術などを大切に活かし続ける精神は、ソーシャルレジリエンス(地域強靭性)の源になっている。AIなどの先端技術と融合させながら、定常型(持続型)の社会デザインを考えていくうえで、桐生モデルは大きな普遍性を持つと私は考えている。
第2章 “志を持って、ふるさとに生きる”青年の実践
私が考えている「社会的強靭性」という概念は、2017年の夏にポーランドを妻と共に旅行して、ワルシャワの歴史地区にある市街広場を囲む伝統的建物環境の復元に伴う市民の不屈の挑戦から学んだことであった。
そのポーランドから帰国して、秋の深まる季節に1通の手紙をもらった。私が大学院で論文指導をしてきた教え子だった。手紙を開きながら彼のことを思い出していた。
もう10年も前のことになろうか。地方都市から、一人の青年の訪問を鎌倉の自宅で受けていた。飄々とした感じだが、芯は強そうだ。キャリアを聞くと驚いた。東京工業大学の大学院経営工学専攻を修了すると、地元の豊田自動織機に入社し自動車の生産管理、品質管理のシステム部門を担当してきたという。天下のトヨタで働いていれば生涯暮らしは安泰では、と思える。ところが、その会社を退社したという。彼が話すには「クルマづくりも面白いのですが、かつて醸造業を営んでいた父の口癖は“酒蔵は地域の文化の醸造所”でしたから、トヨタで学び研鑽したことを地域の文化の生産・品質管理に転換・活用できるのではないか、と考えたのです。日本の地域風土は、産業も、生活にしても地域独特の文化を土壌にして育ちます。そこで地域経営と文化経営を新しく学び直そうと思っています」。私のところに相談に来たのは、多摩大学の社会人大学院が目についたからだという。高給と安定した生活をあえて投げ打ち、現代社会の先端課題解決をする仕事をしたい、という彼、深田賢之さんの志にいたく共鳴していた。
多摩大大学院に推薦し、2009(平成21)年の秋学期から入学して地域経営の勉強を始めた。私が理事を務めている「NPO法人コミュニティビジネスサポートセンター(CBS)」も紹介して勤めることになった。CBSは日本の地域社会の問題解決をコミュニティ(ソーシャル)ビジネスで支える実験的な組織であったので、彼にとって生活の足しとなり、研究と体験の格好のフィールドともなった。CBSの永沢映理事長の「共創と協働の思想」を支えて地域社会デザインも視野に入れた社会事業創造をテーマに2年間働き、その後に1年間地域経済の自立に挑戦する実践組織だった栃木県の那須烏山文化未来塾で研究員となって働いた。大きな体験と修得した叡智をお土産に、2012(平成24)年に故郷である愛知県岡崎市に帰り、すでに岡崎でまちづくりにトライしている大学の先輩の勧めもあって、地元の「NPO岡崎まち育てセンター・りた」に入社し、深田さんの理念である<志をもって、ふるさとに生きる>ことに挑戦している。
その深田さんからいただいた手紙には「ようやく40歳にして所帯を持つことになりました。ついては式に出席いただきご挨拶を」という文面。私は嬉しくなった。ぜひ成長した深田さんとパートナーとなる新婦の佳子さんにも会いたかったし、活躍の現場も見ておきたかった。5月の中旬、よく晴れた汗ばむ季節の岡崎市を訪れた。岡崎は徳川家康公が生れた町だ。
立派に成長した<文化起業家(カルチュラルアントレプレナー)>と私は評したのであるが、結婚式でお祝いを述べた後、彼の父親の正義さんが酒蔵を活用して「地域文化の醸造センター・おかざき塾」を営む長誉(ちょうよ)館を訪ねた。賢之さんが育った「醪(もろみ)」の現場を見る思いがして楽しかった。地方の文化酵母菌を育て続ける教え子を訪ねる愉快な旅を何と形容してよいやら、ワクワクしながら息子に負けない郷土への愛着を持つ父親の正義さんの想いも伺っていた。
賢之さんの目下の仕事は、岡崎市にあるコミュニティの中核となる「東部地域交流センター・むらさきかん」の指定管理者としてセンター長を務め、市民交流や文化事業、子育て支援の施設の運営・管理を展開している。まさに、“まち育て”の現場のど真ん中で市民の暮らしをサポートする仕事である。指定管理とは、行政が直接運営すると費用がかさむので民間のNPOに依頼する制度のように理解されているが、私はNPOとは「ノンプロフィット・オーガニゼーション」ではなく、言ってみれば”非営利“を超えて、”ニュープロフィット(新しい価値)“を生み出すことが大切な考え方となると考えている。すなわち、行政関連施設の運営に当たっても「多様な価値を生み出すマネジメント」が眼目となると思える。そして、将来この発想は行政施設だけでなく、父親の正義さんが運営している民間市民交流施設の「長誉館」のようなものとも連携して、岡崎固有の地域文化の地味豊かな土壌を醸成していくことが目的の一つとなろう。
かつては、何にもましてトヨタのような大企業に就職して安寧な生活を送ることが幸せの条件であった時代があるが、「NPO岡崎まち育てセンター・りた」のメンバーを見ると、まさに「利他(りた)」、すなわち他人や地域の幸せづくりのために働くことが生きる証となっている生き方が意志ある目標になっているように思える。しかも、自動車の生産性や品質を高める手法が、地域文化の創造や品質づくりに着想されていくのも有用な視点だ。この流れは、産業の「モノづくり」から地域の「者(モノ=人)づくり」へのシフトとも捉えられる。その意味で、岡崎市は、「工業都市」から「考業都市」への飛翔を試みる先端的な位置にあるように見える。賢之さんのパートナーとなった佳子さんは、大学で音楽理論を学び、今は福祉施設で働いているという。佳子さんも、社会福祉と同時に将来は岡崎市を「世界一の歌声の溢れる街」にするビジョンを描き実践してくれるのでは、と私は期待しているのである。
優秀な人材が集まり(生み出され)、より良い地域社会の新しい価値創造を担っていく民間主導のモデルこそ、衰退を深める地方・地域の強靭化を支える「防人(さきもり)モデル」となると、私に岡崎訪問は教えてくれた。そして、NPO法人による事業創造とは、組織のアノニマスな遂行から、個人のオニマス(有名性)な情熱や技量がより意味を持つものだと教えてもらった。
岡崎から、東京に戻る新幹線の中で、かつて東海道メガロポリスと呼ばれた沿線に立ち並ぶ巨大社屋や工場を車窓から眺めながら思ったことがあった。トヨタのような巨大でグローバルな企業の未来は、どうなるのであろうか、ということだ。注目の企業家イーロン・マスクが創業した「テスラ」のような電気自動車の先行的企業が生まれ、自動運転技術を巡りグーグルを始めとした世界中の関連企業がしのぎを削っている時代、巨大企業は常に「後塵企業」になってしまうリスクを抱えている。社会的インフラ事業は必要であるから、巨大企業は無くならないであろうが、同一産業類においてトップ企業がその位置を守り続けるのは至難の業であろう。一方で、産業や事業を地元地域側から市民的視点でその存在意味を見たら、どうなるだろうか。限られたエリアの中で、地域特有の市場ニーズに応えようとしたら、市場規模も、事業規模も小さくならざるを得ない。中小企業の存在理由は、それらのニッチなニーズや市場のために存在する。そして、ニッチなニーズは、全世界の多様な地域のそれぞれに存在する。さらに、中小企業のもう一つの存在理由は、現存する産業思想の劇的な転換を素早く読み解き、それを押し上げ、本物にしていく役割を持つことである。この考え方は、世界に先駆けて「ベンチャービジネス」という概念を生み出した恩師の経済学者・中村秀一郎先生から受け継いだものである。中村秀一郎先生は、それまでの日本の中小企業の下請け機能論を排して、地域中小企業こそが冒険的挑戦精神を持つことによって、先端分野や技術のイノベーターの役割を果たすと、喝破した。それが産業強靭性を支える「中堅企業論」である。
私は、その中堅企業(株式会社シンクトゥギャザーのような)が育っている現場の実感を群馬県桐生市で体験したことを、思い出していた。地域産業の持続と発展を支えるのは、まさに地域中小企業の持つ社会思想と産業思想の強靭性にあると思っていたが、岡崎市の市民NPOの「りた」のような新しい価値創造を目指す集合的な複合活動にも(個人の固有な力が基盤にあるが)、生活思想に基づいた暖かく柔らかな強靭性が存在するという啓示を、受けていた。
第3章 美しく、幸せに生きることのできる社会
その温室に入っていくと、柔らかく暖かい空気が身体全体を包み、60種類と言われる育種されたバラの数えきれない花々や蕾から放たれる香りが、今度は体の中からえも言われぬ幸せ感を醸し出していた。より自然に近い土壌を作るために、苦心して調合された土耕栽培床のふんわりした感触も、歩き回ってみると靴底に大地からのメッセージを幾つも送ってくるようで、私には心地よかった。この5400㎡のボタニカルガーデンは、外から見るとどこにもあるような栽培ハウスで幾分そっけない感じがするが、中に入ってみると、どういう訳か子供のころ読んだバーネットの『秘密の花園』の記憶が蘇ってくる。この子供向け物語の主人公は、インドで生まれて両親を亡くし、イギリスのヨークシャのムーア(荒地)に建つ豪壮な叔父の屋敷に連れてこられるメアリという少女であるが、気丈な彼女が発見する「秘密の花園」がドラマティックな舞台となる。10年間、その花園は外界から閉ざされていたのであったが、偶然に扉の鍵を発見した少女は、そこにかつてはバラが咲き乱れていたであろう花園に出会うのである。バラの豊潤な香りを嗅ぐことで、記憶が喚起されて物語を思い出したのは、その温室の存在する意味が私にとっての、あるいは今という時代にとっての『秘密の花園』になる可能性を秘めていることを直感したからかもしれなかった。
今から数年前、私は2冊の本を出版した。その2冊は、それ以前に出した本と同じように反響はさほどのものではなかったが、私にとってはこれからの社会が予感する「時代の感性」のようなものを示唆しようとした試みの最初の著作だった。1冊は、『センス・オブ・ハピネス―希望と幸せを創造する社会へ―』というタイトルで、「幸福を感じ取る力」という意味合いになるが、幸福を創造し受容する力は自分自身にあるということを、この本で言いたかったのだ。このタイトルは、無論レイチェル・カーソンの『センス・オブ・ワンダー』から受け継いだもので、自然など様々な事象が持つ不思議さや感動を受容する柔らかな心の大切さを説いたものを、私としては社会の持つ様々な事象の不思議さや感動のみならず、困難な体験や試練も含めてそれらを『幸福』の範疇でつかみ取る心の柔らかさやレジリエンス(めげない心)の在り様を書き上げようとしたものであった。そのきっかけは、私の教えていた大学での学部ゼミ生・佐藤擁氏から、卒業後の彼の実業を通しての体験談を聞かされたことからである。彼が語るには「仕事の不動産査定で近在のあばら家を訪れた時、空き家だと思っていた家に両目の見えない老女が暮らしており、その惨状が忍びなく彼女を自分のアパートに連れ帰り一緒に暮らしながら、同じような境遇にある老人たちのコーポラティブハウス建設を志すことで何とかそのプロジェクトを実現させた」という、実際の事業物語を聞いたからであった。その教え子から、目の見えないおばあちゃんと暮らすのが楽しかったし、年寄りたちが寄り添って暮らす家づくりも実に愉快だった、と聞いてさらに驚いたのであるが、そこには社会福祉思想のような高邁な理念だけでなく、<みんなで幸せを求めて生きる率直な楽しさ>の感性が実在していた感動が、私にあった。もう1冊は、パリに滞在していた時の体験で、ホテルの部屋に聞こえてきた手回しオルガンの音がきっかけで、駅前の広場にいたオルガン弾きのおじさんと2匹の猫たちと仲良しになり滞在中毎日通い詰めていたが、彼らの話を童話にしたものである。『手回しオルガン弾きと2匹の猫』は、かごの中で寝ている黒ブチの2匹の猫が食事から帰ってきたおじさんに嬉しくてすり寄る姿があまりにもかわいらしく思えて、その幸せ感に感動して書き上げたものである。サブタイトルを「感じる心があれば、幸せの鐘の音が聞こえる」としたのは、どんな境遇の人間や動物であっても、幸せは待つものでも、人から与えられるものでもなく、主体としての自分が感じ、創り上げるものだという実感を表現したかったからであった。すなわち、幸福を直截に感じ掴み取る柔らかな心がこれからの社会の大きな拠り所になるという私の予感と期待が2冊の本を書かせた、と言ってもよい。
私自身,『センス・オブ・ハピネス』の心持を持続させながら、その想いに共感する1冊の本につい最近、出合った。社会学者・見田宗介の『現代社会はどこに向かうのか(2018年)』である。日本を代表する社会学の泰斗・見田宗介氏の考え方には、以前から大きな共感を持っていたが、特に今回の著作には『センス・オブ・ハピネス』の考えと交響性(見田氏の表現)があると感じられた。現代社会が向かうべき方向性について、見田氏は生物学のロジステック曲線の理論を借りて、論究している。この曲線は3期に分類され、第1期は生物種の繁茂のスタートアップ期、第2期が急激な大増殖期、そして第3期の安定平衡期(平衡に失敗すると消滅する)である。これを人類のメタファーとして捉えると、第1期は古代ギリシャで哲学が生まれ、それらが宗教や権威を創出させ、民衆の多くは現世での苦難が来世の幸せを約束させると考えられていた時代、第2期は都市と交易と貨幣の普遍化で、地球上の資本の無限性と永久の成長が、情報と消費の躍動によって担保されていた時代、第3期は経済成長とその破綻、科学と技術の限界性が地球の有限性を露呈させ、人間の生きることの本質的意味を覚醒させる時代、としている。成長の高みを実現させた人類は、これからの生きるというリアリティをどう豊かにしていったらよいのかと、消滅の道を選ばないための叡智を、見田氏は問うのである。それは「経済競争の脅迫から解放された人類は、アートと文学と思想と科学の限りなく自由な創造と、友情と愛と子供たちとの交歓と自然との交感の限りなく豊饒な感動とを、追求し、展開し、享受しつづける」生き方が、求められる時代がその向かうべきところだとする。ある意味、この考え方は楽天主義のそしりを免れないように思えるが、私はそこに『センス・オブ・ハピネス』の人間の善意なる感性が心底に存在していると思えてならないのである。この視点は、見田氏の言う「高度に産業化された諸社会は、これ以上の物質的な<成長>を不要なものとして完了し、永続する幸福な安定平衡の平原(プラトー)の上に立っている」という<高原の見晴らし観>に通底していると、私は考えているのだ。
第4章 ボタニカルイノベーターがデザインする「装知型産業」
その温室に入った時に、私はなぜ心の中で幸せな気持ちになっていたのであろうか。確かにふわっとした空気感の暖かさとパラの香りがその幸せ感を想起させたのかも知れなかったが、どうもそれだけではないように思えた。これまでに何度もイギリスやフランスのパラ園を訪れている。特にイギリスの貴族たちの条件というと、ガーデナー(庭師)の素養、技術を持っていることが求められる。従って、バラ園の多くは貴族の館に付帯している。それらはどれもが立派な庭園である。しかし、私の訪れたその温室は立派さからは程遠い。やはり、咲いているバラたちの風情と色調にあるのではないか、と私には思えた。腑に落ちたのはバラの花々や枝の持つ、言ってみれば“嫋(たお)やかさ”と表現されるものに近い感覚である。「たおやか」とは和言葉であるが、美しくしなやかな様を言う。私にはこれまでに見てきたイギリスなどでの華やかで強い個性のものとは全く印象の違ったバラと思えたが、その新しい品種のバラを創り出した人がいたのだ。
パラづくりには、「育種家」という技術・技量(スキル)と同時にセンスを必要とされる職種があるという。世界には多種多様なバラが存在するが、それらのバラを選び抜き、交配させ、時間を超えて育てていく人たちである。交配させる技術が求められるがそれ以上に必要なのは「先見的イメージ」ではなかろうか。「こんなバラを生み出したい」というイメージ、さらには「バラが内在させるテーマ」という“思想”がなければ、新しいバラは生まれない。彼らを、「ボタニカルイノベーター」と言ってもよい。
そのイノベーターが日本にいたのだ。滋賀県守山市の育種家・国枝啓司氏である。守山市は、日本におけるバラ栽培の草分け的な地域である。ほぼ半世紀前から国枝家ではバラ栽培農家の守山市における中核的な役割を果たしてきたという。2代目の次男に当たる国枝啓司氏は、長男の本家がオランダなどヨーロッパからの新種や珍しい苗の輸入販売事業を展開していることに対し、日本の国内で新しい品種を開発する育種家の道を選んだ。最初は趣味程度の2,3種を手掛けていたが、その開発する意味の大切さに目覚めていく。「バラは、人類の歴史の始めから登場し、人々の生活の中で美の喜びを育ててきた。世界中で色合いも大きさも多種多様なものが存在する。バラが、地域や国の文化を表すものだったら、日本発の文化と個性を持つバラがあってもよいのでは」。そこで「日本から発信するバラの新しい形」、それがブランド名『WABARA』の誕生の思想である。WABARA、すなわち「和ばら」は、ヨーロッパから来た華やかで強い個性を持つ大ぶりな輪郭のバラとは、明らかに違った存在であるように苦心して育ててきた品種だ。それは優しく小ぶりで、しなやかな形状と色合いを持つ。嫋やかさゆえに1輪でも存在の美しさを示すが、花々を集めたブーケになると、色合いのグラデーションが心に迫ってくるようなハーモニーを優しく奏でるようになる。
啓司氏はこれらの、日本発と言えるバラの創発に成功したように思えるが、問題はこの特異な品種のバラを、生活の機微の中でどう生かしてもらえるのか、であったという。
そこで、2人目の「ボタニカルイノベーター」が登場する。国枝啓司氏の子息、国枝健一氏である。健一氏は、大学時代2年間ドイツに留学し、ヨーロッパにおけるバラのみならず他の花々が人々の暮らしの中に溶け込んでいる様を体験している。他家を訪問する時、必ず多くの人々は花々を携えていく。暮らしの中で、美を贈りあっているのだ。
育種家である啓司氏の経営をそのまま受け継ぐのではなく、日本における生活スタイルの中にパラの持つ「美のマネジメントデザイン」をすることが、大切ではないかと考える。これまでの花の流通は、生産農家から花卉市場を通され、町場の花屋から家庭に届けられる。バラに込められた生産者の想いを生活者に素直に伝えたい。そこで生産者から家庭や、花を必要としているレストランなどの店々に直接届けることのできるダイレクトマーケッティングの構想が生まれる。3代目の健一氏は、WABARAの思想も含めて、人々に(国際的な広がりを視野に入れて)直接届ける会社Rose Universeを誕生させた。このファームの企業理念は「世界中の人々が幸せになるバラを創り、届ける」ということであるという。すでに東京などをターゲットにして、WABARAの理念と花を理解していただいている顧客や店々にダイレクトに販売するシステムが稼働している。さらに、これまでに存在していなかったWABARAの風情は、バラの国際市場でも少しずつ評判が高まってきている。ヨーロッパの栽培家の中には、その美に共感しWABARAを育成してヨーロッパ市場で販売する権利を求めてくる動きも出てきているという。
人々の暮らしの中に「美」という種を蒔き美しい生活を創り出す秘密は、まさに『秘密の花園』で育種され、養われてきたバラたちにあるが、彼女たちが今世界にデビューしようとしているのだ。

かつて日本は、繊維産業や化学工業分野で、あるいは自動車やパソコンなどをものづくり大国として世界に輸出してきた。しかし、守山市のRose Farm KEIJIやRose Universeでは、バラという「美しき暮らしのカタリスト(媒介者)」を栽培し販売しようとしているのだ。まだ本当に小さな芽であるが、私は直感する。この動きは象徴的に言えばかつての重厚長大型の「装置型産業」から柔考創発型の「装知型産業」へゆっくりシフトさせ、日本の産業の基底をしなやかに変容させていく予感である。
「装知型産業」とは、資本主義社会を完了させた高原の高みからその先に見える安寧に満ちた社会を彩る風景を形作るビヨンド資本主義の基底となるものであるかもしれない。
私は、地方の地域社会を元気にする企業や事業を支援するある国の支援政策プロジェクトに係ることで、国枝健一氏とRose Farm KEIJIに出会う機会を得た。次代の産業構造を構想するときに、実にラッキーな出会いだったと思っている。
私が考える『センス・オブ・ハピネス』と、見田宗介氏が志向する「次代社会の高みからのビュー」の先に、カルチュラルアントレプレナー(文化起業家)である国枝健一氏たちのローカルイノベーターの活躍を望むことができる。

今、守山商工会議所の研究開発コンソーシアムを立ち上げる事業構想に私は関係しているが、国枝健一さんたちだけでなく、守山市の中小企業群の「知活連携」を実は期待しているのだ。国枝さんの育種栽培と研究開発のハウスの在る施設の目の前に展開する赤野井湾とラグーンである小津袋一帯を形成する赤野井湾漁業組合を筆頭にした中小企業群、あるいは隣接する琵琶湖の生態系を200人規模で研究する「琵琶湖博物館」、水性植物を世界中から収集して育成・展示する珍しい施設群「水生植物公園みずの森」、そしてウオーターフロントに集積したリゾート施設群の多様な社会クラスターを融合させた「定常型社会モデル庭園(パーク)」の構想を提案しているのである。
NPOを通して地域社会と市民の幸せを支える深田賢之氏や、シルバーコーポラティブハウスを軸にしたエイジドコミューンの建設にトライする佐藤擁氏たちの挑戦、そしてスローモビリティ社会を志向しMAYUバスという地域生産車で未来を描く桐生市の中小企業群が、平原の広がりの先にその姿を垣間見せている風景に、守山市の「美と幸せのコミュニティ創造」の構想が加わってくれることに、想いを躍らせているのだ。
第5章 “柔らかに生きる”ことが生み出すもの
先頃(2018年7月)、台風といってもおかしくない大雨が、九州、中国地方、四国など西日本の広域な地域を襲った。観測史上初めてという想定外の雨量が、河川を決壊し農地や市街地を襲い水没させた。山間地は、谷戸に集まった流水が山肌を削り村落の家々を押し流した。それらの家々が古民家風の建物が多かったように思えるのは、長年風雨に耐えてきたものが今回の事態には堪えることができなかった事を示している。まさに、想定外の事態であっても、そのことで諦めることはできない。
何年か前に私は「愛媛大学地域再生マネージャーアカデミー」の塾長である元愛媛大学教授の森賀盾夫氏の招きでアカデミーで講演させてもらった。森賀先生は、地域産業遺産の発掘者であり社会災害史のユニークな研究を続けているが、彼に紹介された農業者がいた。その畏敬する人物が西山敬三さんである。7月の大雨が地域に大被害をもたらしたという報道で、西山さんと農地はどうなったかと心配していた。案の定、自分を造語である「自適農」と呼ぶ西山さんは、愛媛県の松山市郊外で農業を営んでいるが、斜面の耕作地のほとんどを大雨で流され、壊滅的な被害を受けたという。しかし、大雨の去った次の日から鍬を持って表土を流されて荒れた傾斜地にキュウリやバナナなどの作付けを始めている。「肥沃な表土が流された後の真砂土には何が合うのか、次の植生の在り方を考えている」とFacebookで報告している。さらに「一粒の種に、一本の苗に希望を持つ、それが自適農だ」と言っている西山さんの心を思って、私は涙した。しかし「社会強靭性」を涙だけで語ることはできない。さらに論理や理論だけでも語ることも容易なことではない、とこのテーマを考えてきた私は思う。
ポーランドのワルシャワで出会った、平和と愛ある社会を希求する信念を看護婦のスタイルで意思表示する少女も、大企業を辞めて地方の非営利企業に勤めることで地域に生きる真の幸せを見出そうとしている青年も、そして大工場ではなく町場の小さな工場からでもローテックを駆使した産業思想を生み出そうと挑戦している「ビジネス草莽」の人々も、何か<動かしがたい強靭な心>を持っている、と私には見える。
西山さんが、自分の存在を「自適農」と呼ぶとき、それは自然に抗うことでなく、自分自身で自然の荒ぶれた現象でも素直に適応していく姿と心を表現しているのだと思う。生きていく信念は不動であっても、現実の事態には自在に適応していく「柔らかな生き方が求められる時代」が「社会的強靭性」を再び見出し、社会の奥底に流れている強い意志と柔らかく生きていく記憶を復元させる時代が来ている、と私は考えているのだ。

参考文献
第1章
・『ポスト・ヒューマン誕生』レイ・カーツワイル NHK出版 2007年
・『電脳世界』ポール・ヴィリリオ 産業図書 1998年
・『ふりかえれば、未来』木村尚三郎 PHP 1992年
第2章
・『21世紀型中小企業』中村秀一郎 岩波新書 1992年
第3章
・『秘密の花園』フランシス・バーネット 新潮文庫 2016年
・『センス・オブ・ハピネス』望月照彦 日本紀行 2013年
・『手回しオルガン弾きと二匹の猫』望月照彦 日本紀行 2013年
・『現代社会はどこに向かうか』見田宗介 岩波新書 2018年
・『センス・オブ・ワンダー』レイチェル・カーソン 新潮社 1996年
第4章
・『園芸業界初!世界で唯一の「和ばら」で世界展開を目指す』中河桃子 日本人材機構HP 2018年
第5章
・『自適農の地方移住論』西山敬三 創風社出版 2017年